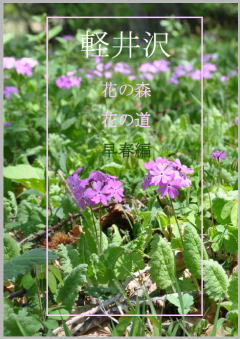芒種~処暑の頃 (6月6日頃~8月23日頃 / from ~June.6 to ~August.23)
夏の草木花 No.71
キツネノボタン
(狐の牡丹)
花:キツネのボタン
実:キツネのボタン
[きつねのぼたん]
- Ranunculus silerifolius-
|
タイトル/Title : キツネノボタン(狐の牡丹) |
科 / Specific family : キンポウゲ科
学名 / Scientific name : Ranunculus silerifolius
英名 / English name :
|
撮影場所 / Place : 軽井沢町追分
撮影日 / Date : 2009/ 6 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
狐にも 狐の牡丹 咲きにけり
~ 相生 垣瓜人 ~ |
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
軽井沢では全域で見られます。特に、山道沿いの少し涼しい場所でよく目にします。軽井沢では、5月頃から8月頃まで見られる夏の花ですす。
花の表面が光沢を帯びていて、日光を受けて、キラキラ輝く姿は美しいです。この光沢は、キンポウゲ科の特色で、馬の脚形(ウマノアシガタ)や蛙傘(ヒキノカサ)も、同じように、花弁に光沢を持っています。
日本の代表的なキンポウゲ科の花である、狐の牡丹、馬の脚形、蛙傘に、動物の名前が付いているというのは、とても面白いですね。昔の人の、ネーミングのセンスが感じられます。
狐の牡丹は、花もユニークですが、その実は、もっとユニークな形をしています。左の写真のように、まるで金平糖のようです。思わず摘まんで、なめて見たくなりますが、おっと、それは危険。実は、狐の牡丹は、有毒植物。なめたぐらいでは、命に関わるほどではありませんが、お腹を抱えてトイレにこもらなければいけなくなるかもしれません。。
キンポウゲ科の植物は、アネモニンを含むため、大量に摂取すると、心臓の機能に影響を与え、死に至る場合もあります。
名前の由来ですが、金平糖のような実を、狐のボタンに喩えたのだと思っていました。しかし、よくよく調べると、葉の形が、牡丹に似ているのがその理由のようです。
花を咲かせる前は、牡丹だと楽しみにしていたのに、いざ咲いてみると違う花だった。これは、狐に化かされた…と昔の人が考えたのでしょう。
|
夏の草木花 No.72
クモキリソウ
(雲切草)
[くもきりそう]
- Kumokirisou -
|
タイトル : クモキリソウ(雲切草) |
科/ Specific family : ラン科
学名 / Scientific name : Liparis kumokiri
英名 / English name : |
撮影場所 / Place : 軽井沢町追分
撮影日 / Date : 2009/ 6 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
- - - 俳句募集中です。あなたの力作、お待ちしています。- - -
メールにてご応募下さい- - - |
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
雲切草という詩情溢れる名前の夏の花です。
花の形が、とてもユニークなランの仲間で、トンボソウやミズトンボの花に似ています。
たくさんの妖精が、手を広げて空を舞っているような姿は、一度見ると忘れられません。それは、名前の如く、雲を切って空を飛んでいるかのようです。
軽井沢では、限られた場所に生息しています。針葉樹などの木影にひっそりと生えていますが、見つけるのは、至難の技です。
もし、軽井沢で雲切層草に出会えたなら、それは、とてもラッキーなことです。
私の知っていた生息場所でも、数年前の伐採と剪定により、雲切草の姿が消えてしまいました。
樹木の剪定や、森林の下刈りは必要ですが、樹木の下で生きている山野草にも配慮してもらいたいものです。
|
夏の草木花 No.73
クリンユキフデ
(九輪雪筆)
[くりんゆきふで]
- Kurin yukifude-
|
タイトル : クリンユキフデ (九輪雪筆) |
科/ Specific family : タデ科
学名 / Scientific name : Polygonum suffultum
英名 / English name : -
|
撮影場所 / Place : 軽井沢町旧軽井沢
撮影日 / Date : 2005/ 6 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
- - - 俳句募集中です。あなたの力作、お待ちしています。- - -
メールにてご応募下さい- - - |
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
軽井沢では、旧軽井沢から離山周辺の森林を中心に生えています。適度にあかるい森の下に、葉に包まれた穂状の花を咲かせます。
温かい地方では、春早いブナなどの広葉樹の森で見られますが、寒冷な軽井沢では、6月くらいに咲いているのを見かけます。したがって、普通は春の花としている事が多いですが、軽井沢では、初夏の花として紹介します。
”九輪雪筆”という名前の響きは、とても素敵です
この花で特徴的名なのは、葉っぱに包まれるようにして花茎が出ていることです。いわゆる、托葉(たくよう)と言われる葉っぱです。
名前の由来は、花穂が、まるで白雪の筆のようだからという説がですが、実際は、白雪というほどの白さはなく、くすんだ白色をしています。むしろ、同じタデ科の仲間で、春虎の尾(ハルトラノオ)の方が、より白く綺麗な花を咲かせるので、そちらの方に、雪筆という称号に相応しい気がします。
人間にも、名前が立派過ぎると、名前負けすると言いますが、この花には失礼ですが、名前負けしているかなという気がします。
|
夏の草木花 No.74
クサフジ
(草藤)
[くさふじ]
- Kusafuji -
|
タイトル : クサフジ(草藤) |
科/ Specific family : マメ科
学名 / Scientific name : Vicia cracca
英名 / English name : Tufted vetch
|
撮影場所 / Place : 軽井沢町追分
撮影日 / Date : 2008/ 7 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
草藤や 驟雨はれたる 水の照り
~ 中川 暁雨 ~
|
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
真夏の太陽の下で、他の草に絡まりながら、勢力を広げる夏の花です。藤も他の木に絡みつき、逞しいほど勢力を拡大させますが、この草藤も、名前に違わず、草むらの一角を占領するほどの勢いです。
ごく稀に、アルビノである白い草藤を目にします。その場合は、アルビノ種だけの群落を形成しているので、遠目にも分かります。あなたの町でも、注意して探してみれば、見つかると思いますので是非、探してみては如何でしょうか?
日本全土で見られますが、軽井沢では、蔓性の夏の花の中でも、最もよく見られる花の一つです。似たような花に、弱草藤(なよくさふじ)という花がありますが、こちらは外来種で、花の咲く時期が初夏ぐらいで、花期も短いです。どちらも、Viciaという属名を持ちます。これは、巻き付くという意味のラテン語”vincire”に由来します。
|
夏の草木花 No.75
マタタビ
(木天蓼)
[またたび]
- Matatabi -
|
タイトル : マタタビ(木天蓼) |
科/ Specific family : バラ科
学名 / Scientific name : Actinidia polygama
英名 / English name : Silver vine
|
撮影場所 / Place : 軽井沢町追分
撮影日 / Date : 2005/ 8 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
またたびの 花をやさしと
折れば匂ふ
~山口青邨~
|
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
夏になると、軽井沢の野山のあちこちに、白い葉っぱが目立ち始めます。マタタビの葉っぱです。北海道や中部地方以北の寒冷な地域には、赤みを帯びた白い葉のミヤママタタビが生えますが、軽井沢では、白組のマタタビの勢力が強いです。
猫にマタタビという言葉があるように、マタタビの実は、猫に絶大な陶酔効果を持っています。
花は、ふっくらした梅の花のような形をしていて、仄かな良い香りがします。
大きな薬効があるのは、虫こぶが付いて、ボコボコした実で、焼酎漬けにします。木天蓼酒という薬用酒の出来上がりです。疲労回復、滋養強壮の薬効があります。 |
夏の草木花 No.76
マツバギク
(松葉菊)
[まつばぎく]
- Matsubagiku -
|
タイトル : マツバギク (松葉菊) |
科/ Specific family : ツルナ科
学名 / Scientific name : Lampranthus Spp.
英名 / English name : Fig marigold, Trailing ice plant |
撮影場所 / Place : 軽井沢町借宿
撮影日 : 2005 /7 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
蛇の尾の かくれきらずに 松葉菊
~ 永田 耕一郎 ~ |
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
南アフリカ原産の花です。多肉質で、松のような葉をしている事から松葉菊と呼ばれています。
水はけの良い場所を好むので、写真のような日当たりの良い石垣などに植えるとよく育ちます。耐寒性は、さほどないのですが、軽井沢でも多年草として定植され、よく見かけます。
学名のLamprantsus (ランプランタス)は、ギリシャ語で、「光り輝く花」という意味です。その名の通り、日光を浴びると、花弁が開き、光沢のある花がテカテカと日光を反射して輝きます。
南アフリカには、数多くのルツナ科の植物が自生し、約2000種類を超えます。日本から最も遠い国の一つですが、南アフリカ原産の園芸種が多い為、日本人には馴染みのある植物も多いです。例えば、Zantedeschia
aetiopica (ザンテデスギア・エチオピカ
)などがあります。さて、ここで問題です。この花は日本では何と呼ばれているでしょうか?ヒントはサトイモ科です。
|
夏の草木花 No.77
ミツバ
(三葉)
[みつば]
- Mitsuba -
|
タイトル : ミツバ (三葉) |
科/ Specific family : セリ科
学名 / Scientific name : Cryptotaenia japonica
英名 / English name : Mitsuba |
撮影場所 / Place : 軽井沢町追分
撮影日 / Date : 2008/ 7 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
- - - 俳句募集中です。あなたの力作、お待ちしています。- - -
メールにてご応募下さい- - - |
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
ミツバは、春の山菜として有名で、スーパーの店頭などにも並んでいるポピュラーな日本のハーブ(香り野菜)です。英語名も、日本語読みの”Mitsuba”となっています。
スーパーでも買って食べる事が出来ますが、野生のミツバの方が味、香りとも優れています。あまり知られていませんが、根っこもきんぴらなどにして食べられます。
軽井沢では、半日陰の道路沿いや林沿いに生えているのを見かけます。自生している場所は、点在していますが、地味な草なので、単なる雑草としか見られてないことが多いです。
夏に、地味な白い花を咲かせます。花の一つ一つは小さいですが、間近でよく見ると、可愛らしいです。
実はよく付き、庭などに植えておくと、零れ種でよく増えます。家庭菜園の植えておくと、それほど手間を掛けずに、ミツバの味を楽しめます。
|
夏の草木花 No.78
ハンショウズル
(半鐘蔓)
[はんしょうづる]
- Hanshoduru -
|
タイトル : ハンショウズル(半鐘蔓) |
科/ Specific family : キンポウゲ科
学名 / Scientific name : Clematis japonica
英名 / English name : |
撮影場所 / Place : 軽井沢町杉瓜
撮影日 / Date : 2009/ 6 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
- - - 俳句募集中です。あなたの力作、お待ちしています。- - -
メールにてご応募下さい- - -
|
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
軽井沢では、山沿いの道などで見ることができますが、生息数は少なく、あまり見かけません。
本州や九州に自生しますが、南方のものと比べると、軽井沢のものは、花の色が白っぽいようです。
奥山に行くと、深山半鐘蔓という、半鐘蔓の高山種を見ることができます。
名前の半鐘蔓は、花の形が、お寺の鐘(半鐘)に似ていて、つる性であることが由来です。下向きに咲く薄紫色の花は、とても可愛いです。
林縁には、つる性の草木が多いです。このような森林の縁に生息する植物群は、”マント群落”と呼ばれます。マントの意味する所は、マントのように森林に覆いかぶさり、日光や強風が直接、森林の中に入るのを防ぎ、森林内の環境を保持するという事にあります。人間の羽織るマントと同じような効果です。
|
夏の草木花 No.79
アカツメクサ
(赤詰草)
[あかつめくさ]
- Akatsumekusa -
|
タイトル : アカツメクサ(赤詰草) |
科/ Specific family : マメ科
学名 / Scientific name : Trifolium pratense
英名 / English name : Red clover, Purple clover, Wild clover |
撮影場所 / Place : 軽井沢町借宿
撮影日 / Date : 2005/ 6 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
- - - 俳句募集中です。あなたの力作、お待ちしています。- - -
メールにてご応募下さい- - -
|
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
野原に生えるピンクのクローバーです。花色は、赤紫色なので、レッドクローバーともパープルクローバーとも呼ばれます。日本名でも、赤詰草、紫詰草と呼ばれます。
白詰草よりも大柄で、時々、茎立ちして、膝丈ぐらいまで伸びているものも見かけます。
白詰草と同様に外来種で、日本には、明治初年に北海道に移植されました。畜産業用に、土壌改良や飼料など使われ、今では、日本全国にその分布を広げています。
|
夏の草木花 No.80
シロツメクサ
(白詰草)
[しろつめくさ]
- Shirotsumekusa -
|
タイトル : シロツメクサ (白詰草) |
科/ Specific family : マメ科
学名 / Scientific name : Trifolium repens
英名 / English name : Dutch clover, white clover, Trefoil |
撮影場所 / Place : 軽井沢町鳥井原
撮影日 / Date : 2006/ 6 |
お気に入りの俳句 / Favorite Haiku :
- - - 俳句募集中です。あなたの力作、お待ちしています。- - -
メールにてご応募下さい- - -
|
夏の花 エッセイ / Essay of summer flower :
白詰草というよりは、クローバーといった方が通りが良いでしょう。幸福の徴(しるし)として有名な、四葉のクローバーで同じみの花です。
元来は、ヨーロッパ原産の草花ですが、現在では、日本のみならず、全世界に広がっています。
日本に入って来たのは歴史が古く、16世紀の後半と言われています。ヨーロッパから送られてきた荷物の緩衝材として入れられていたのがクローバーの枯れ草。その中に混じっていた種が発芽し、日本全土に広がっていきました。
今では、牧草としてだけではなく、優秀な初蜜の蜜源として利用されています。
|
|
更新情報:
2012.6.4 レイアウト修正
2010.8.21
夏の草木花 Page.8 エッセイ追加
2010.7.10
夏の草木花 Page.8 新規追加
|